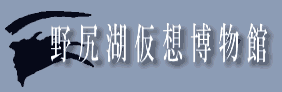

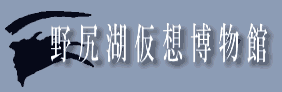  |
|
|
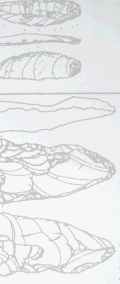 |
TOP :: 野尻湖の遺跡 :: 野尻湖発掘入門編 2003/03/08 野尻湖へ行こう野尻湖は長野県北部の信濃町というところにあります。周りを妙高、黒姫、斑尾といったスキー場に囲まれ、冬には雪の多い地方です。もちろん湖底発掘の期間中にも雪が積もっていて、発掘中に一日くらいは雪が降ることがあります。  14次発掘のグリッド初日の様子 湖底発掘では3月末を選んで野尻湖の干上がった湖底を掘ります。干上がってはいても地層からは水が絶えずしみ出し、地面はぬかるんでいます。長靴を忘れないでください。現場に到着したら受付をすませ、宿舎に荷物を置いてきてください。現場の入り口付近に大きな看板がでていて、あなたの担当するグリッドの場所が書いてあります。担当グリッドへ行けば、結団式などで顔を見た知り合いが発掘をしているはずです。班長を呼び、指示をもらいましょう。 野尻湖の発掘は学術的な目的をもった研究活動です。発見した化石は持ち帰れません。
現場での作業にはいろいろな危険がありますし、発掘にはきちんとしたルールがあります。それを守って楽しく発掘しましょう。 グリッドを掘り進める
遺物が見つかったら湖底から見つかる化石や遺物のほとんどは水を含んで非常に壊れやすい状態になっています。移植ごてを使い、地層のラミナに沿って少しずつ地面を削っていきます。地面をしばらく削っていくと、そこに周りとはまったく色の違う部分が突然現れます。鮮やかなオレンジ色〜肌色をしていれば、それは骨の化石かもしれません。茶色〜黒色で繊維が見えたら植物の遺体、緑〜白色で円形だったら貝の化石、といった具合に化石や遺物にはそれぞれの特徴があります。遺物が見つかったらまず班長に声をかけてください。そして専門班の人にきてもらい、遺物の種類や取り上げ方を教えてもらいます。 第14次発掘では「たしかめ掘り」第15次発掘からは「産状確認法」といった、遺物と地層の関係をより精密に記録するための方法が用いられています。重要な試料についてはこのような観察を行なうため、専門家に後を引き継ぎます。それ以外の小さい遺物の場合は遺物の形がわかるように周辺を注意しながら掘り、記載を行ないます。
専門班に鑑定をしてもらったら、記載係や班長は発見された遺物に通し番号をつけます。
次に記載係が、遺物の位置をコンベックス(巻尺)とグリッドに張られた水糸を使って調べ、測量班と協力して遺物の標高を記録します。他にも遺物のスケッチ、向き、発掘時につけてしまったキズ、遺物と地層との関係、地層の層相、発見者氏名などを記録します。記載係は高校生以上が担当します。 専門班によってはここで化石を発見した記念にカードを発行してくれるところもあります。記載の終わった試資料はポリ袋などに移され、記載した書類とともに試資料整理窓口へ運ばれます。
発掘は日が昇っている間しかできず、小中学生から一般まで幅広い年齢層が参加しているので、発掘期間中、朝は少し早めの7:00から朝食で、8:30には現場に入って発掘が始まり、午前のおやつ、昼食、午後のおやつをはさんで午後4:00には発掘は終わってしまいます。そのあと夕食などをすませたら、近くの小学校などに全員集まってまとめの全体集会に参加します。  体育館に集まって全体集会 集会では今日の発掘の成果の報告を聞いたり、それについての討論や連絡事項の伝達などがあります。子供達のスケジュールはこれで終わりです。宿舎に戻って休みます。専門班はこの後も会議や試資料の整理を続けたり、酒を飲んだり酒を飲んだりしています。
遺跡の研究では、現場での発掘はいわばスタートに過ぎません。湖底から取り上げられた化石や遺物は大変もろく、大型品はセッコウで周りを固定された状態になっています。遺物はセッコウを外したりクリーニングした後樹脂をしみ込ませて強化するなどの処理を経て博物館に収蔵され、専門家による研究が行なわれます。これらの作業は何年もかかって行なわれ、野尻湖ナウマンゾウ博物館研究報告という本にまとめられます。専門グループの活動には、野尻湖発掘と同様に誰でも参加することができます。 野尻湖の専門グループ
|